第三節 人法一箇(体一)の法義に背く大罪
大御本尊への信仰を捨てた創価学会をただす―矛盾のスパイラルにおちいった創価学会
nnnn 日蓮大聖人の仏法には「人法一箇(体一)」という法義があります。これは、人本尊と
法本尊が一体であるという意味です。
人本尊と法本尊が一体であることについて、日寛上人は、
「本地難思の境智の冥合・本有無作の事の一念三千の南無妙法蓮華経を証得するを、久遠元初の自受用身と名づくるなり。此の時、法を尋ぬれば人の外に別の法無し、人の全体即ち法なり。此の時、人を尋ぬれば法の外に別の大無し、法の全体即ち人なり。既に境智冥合し人法体一なり」(観心本尊抄文段・文段二〇二頁)
と仰せられ、久遠元初の自受用身(人)と、事の一念三千の南無妙法蓮華経(法)が一体である旨を指南されています。
創価学会が編纂した『仏教哲学犬辞典』にも、「人法一箇」について、
「日蓮大聖人の仏法において、大本尊と法本尊は、その名は異なるが、その体は一つであること」 (該書第三版一三二〇頁)
と説明しています。
すなわち人法一箇とは、「久遠元初の自受用身」たる末法の御本仏日蓮大聖人を大本尊とし、「本有無作の事の一念三千の南無妙法蓮華経」を法本尊として、法即人、人即法の御本尊を指します。
日寛上人は、
「本地難思の境智冥合、久遠元初の自受用報身の当体、事の一念三千、無作本有、南無本門戒壇の大本尊」 (当家三衣抄・六巻抄二二五頁)
と仰せられ、本門戒壇の大御本尊は事の一念三千の法であるとともに、「久遠元初の自受用報身如来の当体」すなわち末法の御本仏日蓮大聖人の御当体であることを説示されています。
今回、創価学会は、人法一箇の大御本尊を信仰の対象から外しましたが、これを端的に言えば、日蓮大聖人の御当体であり御魂魄である大御本尊を放棄したということです。
条文の上では「日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ」ながら、信仰の上では日蓮大聖人の御当体に手を合わせないというのですから、これほど道理に合わない話はありません。
まさしく創価学会は救い難い矛盾のスパイラルにおちいったと同時に、自らの信仰を否定していると言うべきです。
第二節 日蓮大聖人の出世の本懐を捨てる大罪
大御本尊への信仰を捨てた創価学会をただす―矛盾のスパイラルにおちいった創価学会
日蓮大聖人は、大御本尊を出世の本懐とされることについて『聖人御難事』に、
「清澄寺と申す寺の諸仏坊の持仏堂の南面にして、午の時に此の法門申しはじめて今に二十七年、弘安二年雅なり。仏は四十余年、天台大師は三十余年、伝教大師は二十余年に、出世の本懐を遂げ給ふ。其の中の大難申す計りなし。先々に申すがごとし。余は二十七年なり。其の間の大難は各々かつしろしめせり」 (御書一三九六頁)
と仰せられ、弘安二年十月十二日に本門戒壇の大御本尊を図顕されました。
この御文に示された大聖人の出世の本懐について、総本山第二十六世日寛上人は『観心本尊抄文段』に、
「問う、弘安の御本尊、御本懐を究尽するや。答う、実に所問の如し、乃ち是れ終窮究竟の極説なり(中略)吾が大聖人は文永十年四月一一十五日に当抄を終わり、弘安二年、御年五十八歳の十月十二日に戒壇の本尊を顕わして四年後の弘安五年、御年六十一歳十月の御入滅なり(中略)天台・蓮祖は同じく入滅四年已前に終窮究竟の極説を顕わす、寧ろ不思議に非ずや」 (文段一九六頁)
と教示されています。
これらの御文から、大聖人の出世の本懐は「弘安二年、御年五十八歳の十月十二日」に図顕された「戒壇の本尊」であることは明白です。
また、日寛上人が、
「弘安二年の本門戒壇の御本尊は、究竟の中の究竟、本懐の中の本懐なり。既に是れ三大秘法の随一なり、況んや一閻浮提総体の本尊なる故なり」(観心本尊抄文段・文段一九七頁)
と教示されるように、この大御本尊こそが三大秘法随一の御本尊であり、末法の一切衆生が帰依すべき、究竟中の究竟たる御本尊なのです。
現在、創価学会総本部に安置される通称「慈折広布の御本尊」を認められた第六十四世日昇上人も、
「久遠本仏たる宗祖日蓮大聖人は南無妙法蓮華経をお唱へ出された年から二十七年即ち弘安二年に出世の御本懐たる本門戒壇の大御本尊を一切衆生に総与遊ばされたのであります」
(大白蓮華・昭和二七年六月号四頁)
と明確に指南されています。
今回、創価学会が、本門戒壇の大御本尊を信仰の対象としないと宣言したことは、まさ
しく御本仏日蓮大聖人の出世の本懐を放棄したことになるのです。
七五三祝いはどこでー神道・民間信仰
諸宗教破折2
千歳飴を持ち、きれいな着物で着飾った子供たちを目にするこの時期、子や孫が七五三の年齢に当たっている家族は、着物の着付けや写真の予約、そしてお参りはどこへ行こうかなどと、お祝いの準備に忙しい。
七五三祝いとは
現在のように、三歳の男女児、五歳の男児、七歳の女児の祝いとして十一月十五日に行われるようになったのは、江戸時代の中期と言われている。
かつて三歳の男女の祝いは、それまで剃っていた髪を伸ばし始める「髪置の式」が行われた。
また五歳の男児の祝いは、大人と同じ装いをする「袴 着の式」。
そして七歳の女児の祝いでは、着物に直接縫い付けてある、帯代わりの紐を取り除く「帯解きの式」が行われ、氏神に参詣したのが七五三祝いの始まりとされている。
このような成り立ちから、現在では、我が子の健やかな成長を願って、有名な神社に出向いて祈祷をしてもらいたいという親が多いようだ。
コロナ禍で分散傾向ではあるものの、全国的に見て多くの人出が見込まれるのは、やはり明治神宮や太宰府天満宮をはじめ、伏見稲荷大社、住吉大社、鶴岡八幡宮、熱田神宮、氷川神社などの神社が主であろう。
とはいえ、かわいい我が子の成長を本気で願う親ならば、それを託する対象も、よく吟味してしかるべきである。
何に祈願してる?
ちなみに東京都渋谷区にある明治神宮には、国民の恋慕の想いから明治天皇と昭憲皇太后が御神霊として祀られている。 また、福岡県太宰府市にある太宰府天満宮には、学問の神として菅原道真が祀られている。果たして、これらの対象はその願いを叶えるに値する神であるのかと言えば、これらは単に歴史上の著名な人物を神仏へと昇格させて崇めているに過ぎない。仏法の眼をもって見れば、それらの人物も、所詮は己の煩悩すら解決できない一介の凡夫である。それをもって人々の願いを叶えてくれる神であると考えるのは、全くの誤りであると言えよう。
また、京都市伏見区にある伏見稲荷大社には、欽明天皇の即位にまつわる『日本書紀』の記述に登場する、キツネともオオカミとも知れぬものを神の使いとして重んじている。 いずれにせよ、所詮は人間より境界の低い畜生である。 わざわざ低俗な畜生を拝むならば、感応道交の理の上から自らが畜生に同ずることになり、人格を低落させることになるのである。
さらに大阪市住吉区にある住吉大社には『日本書紀』等に出てくる底筒男命・中筒男命・表筒男命・神功皇后が祀られ、神奈川県鎌倉市にある鶴岡八幡宮には、応神天皇・比売神・神功皇后、名古屋市熱田区にある熱田神宮には、
天照大神等の神々、さいたま市大宮区にある氷川神社には、須佐之男命・稲田姫命・大己貴命が祀られているが、これらはあくまで神話上の神に過ぎず、これらが人々を救うことなどできようはずもない。
ここに列挙した以外の神社についても、その内容はおおむね推して知るべしであろう。
正法の寺院に詣でよう
そして最も大事なことは、これらの神社は人々を救う力がないばかりでなく、日蓮大聖人が『立正安国論』に、
「正法の法味に飢えた神々は天上に帰り、空になった神社には悪鬼魔神が棲みついて種々の災難を起こしている(趣
意)」(御書 234ページ)
と仰せのように、正法に背く結果として、現今のコロナ禍の如き三災七難が起こっているという現実を、よく知ることである。
大聖人が『四条金吾殿御返事』に、
「仏法と申すは道理なり」 (同 1179ページ)
と御教示のように、正しい宗教とは、普遍妥当性を有した、道理に適った教えでなくてはならない。
無上の宝である我が子の成長を真に願うのであれば、悪鬼魔神が巣食う神社に詣でるのではなく、文証・理証・現証の上からも末法の正法たる大聖人の教えを奉ずる日蓮正宗の寺院に参詣して、祈念を願うべきである。
第一節 今回の会則改変について
大御本尊への信仰を捨てた創価学会をただす―矛盾のスパイラルにおちいった創価学会
創価学会は、従来の会則(平成十四年改変)のうち、教義条項にあたる、
「第2条 この会は、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の御書を根本として、日蓮大聖人の御遺命たる一閻浮提広宣流布を実現することを大願とする」 (聖教新聞・平成一四年四月一日付)
との条文を、今回の改変で、
「第2条 この会は、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、根本の法である南無妙法蓮華経を具現された三大秘法を信じ、御本尊に自行化他にわたる題目を唱え、御書根本に、各人が人間革命を成就し、日蓮大聖人の御遺命である世界広宣流布を実現することを大願とする」 (本書137頁参照)
としました。
すなわち、信ずる対象について、それまでの条文にあった「一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊」の文言を「根本
の法である南無妙法蓮華経を具現された三大秘法」と変え、「大御本尊」という言葉を抹消しました。
これをもって、会長の原田稔は、
「弘安2年の御本尊は受持の対象にはいたしません」(本書139頁参照)
と宣言したのです。
会則改変の流れ ↓
nnnn
はじめに
大御本尊への信仰を捨てた創価学会をただす―矛盾のスパイラルにおちいった創価学会
今般、創価学会は会則を改変し、その説明として聖教新聞紙上に「弘安2年の御本尊は受持の対象にはいたしません」と発表しました。
これは、創価学会の前身である創価教育学会が昭和五(一九三〇)年に設立されて以来、八十数年にわたって会員が等しく信仰の対境として尊崇してきた宗祖日蓮大聖人弘安二年十月十二日所顕の本門戒壇の大御本尊を放棄することを意味します。
信仰の世界において、礼拝の対象となる本尊は最も重視されなければなりません。
今回、創価学会が行った本尊義の改変は、教団の存立基盤を揺るがし、八十数年の歴史を覆す大事件です。
日蓮大聖人を御本仏と立てながら、大聖人出世の本懐たる大御本尊を放棄するという致命的な過ちを犯した創価学会は、それを繕うため、いくつかの異説を唱えざるをえない状態に至りました。
まさしく創価学会は、はてしない矛盾のスパイラル(らせん状の進行)におちいったと言えましょう。
本書は、創価学会首脳部に誑惑される学会員を目覚めさせるため、会則を改変したことに伴う創価学会の本尊義と、それを言い繕うための邪説を破折するものです。
本書によって、迷える学会員が一人でも多く、本門戒壇の大御本尊まします富士大石寺の正法に帰依することを祈ってやみません。
日蓮正宗宗務院
大御本尊への信仰を捨てた創価学会をただす―矛盾のスパイラルにおちいった創価学会
第一章「大御本尊は受持の対象にはしない」との邪義を破す
nnnn第一節 今回の会則改変について
第二節 日蓮大聖人の出世の本懐を捨てる大罪
第三節 人法一箇(体一)の法義に背く大罪
第四節 御歴代上人の御指南に違背する大罪
日應上人 日亨上人 日開上人 日昇上人 日淳上人 日達上人
第五節 歴代会長の指導との矛盾
第六節 教義・信仰基盤の崩壊
第二章 大御本尊放棄を言い繕うための邪説を破す
nnnn第一節 「御本尊を創価学会が認定する」という邪説
①凡夫集団に御本尊を認定する資格はない
②「創価学会は広宣流布を推進する仏意仏勅の教団」という妄言
第二節 創価学会の「三大秘法説」を破す
①「三大秘法を信ずる」とは観念的信仰
②一大秘法抜きの三大秘法は邪説
③「文字曼荼羅は等しく本門の本尊」という邪義
第三節 「これまでの本尊観は世界広布を阻害する」との邪説
①御遺命の戒壇を否定する大罪
②根本の御本尊」と「御書写の御本尊」との立て分けを否定する大罪
③「慈折広布の御本尊」 (創価学会常住御本尊)について
第四節 創価学会の信仰の誤り
原田会長は、「受持即観心」について説明するなかで、次のように述べています。
「御本尊の力用は、自行化他の実践があるところに発揮されるのであります。大聖人の御本尊は、『法華弘通のはたじるし』すなわち民衆救済のための御本尊であり、広宣流布のための御本尊であります。御本尊は広宣流布の誓願、信心で拝してこそ御本尊の力用が発揮されます」 (本書139頁参照)
この説明から、創価学会が、大御本尊を放棄したことによって、御本尊よりも衆生の信行を主体とするという、本末転倒の信仰論を主張し始めたことがわかります。
①正境なくして利益なし
②言葉のみの広宣流布をかかげる創価学会
第三章 「大石寺は謗法の地」との妄言を破す
nnnnnnnnnnnn第四章 会則改変の経緯
nnnnここで、創価学会規則の制定および創価学会会則の制定と改変について、その経緯に触れておきます。
第一節 創価学会規則と創価学会会則の制定
第二節 「感情や歴史的な経過を踏まえ」との欺瞞

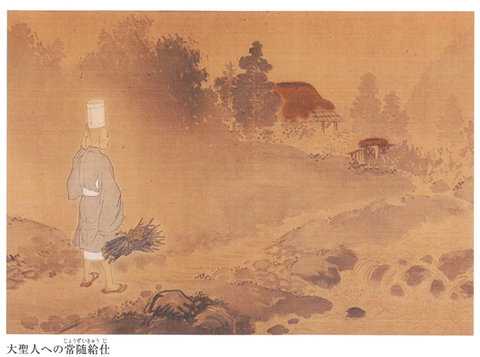

1140夜:前世を記憶する子どもたち
2021年10月21日
(さらに…)
共有: